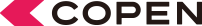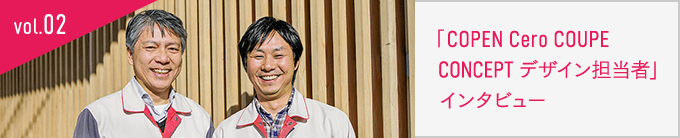実車を前にして、公道での走りを想像する。

東京オートサロン2019が開催される前、「COPEN Coupe」の実車に触れる機会があった。世界に1台しかないそのCoupeは、工房の中に置かれていた。その姿は、2016年の東京オートサロンにコンセプトカーとして出展されていた「COPEN Cero COUPE CONCEPT」とほとんど変わっていないように見受けられた。
外観上の違いといえば、フロントウインドウの枠がシルバーからブラックになっていることと、ドアウインドウとリヤウインドウの間のパネルがカーボン調でないことぐらいだ。ホイールはBBS製の鍛造アルミホイールを装着している。

開発スタッフから許可が出たので、クルマに触れてみる。ドアを開け運転席に座る。アクティブトップが取り外され、ハードルーフはCFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastics)を採用している。軽量で素材も薄いので、ヘッドスペースはたっぷりと確保されている。これならモータースポーツに参加したとき、ヘルメットをかぶっても十分に頭上に余裕がある。

ハンドルはMOMO製の革巻。小径なのでスポーティな雰囲気にさせてくれる。リヤのガラスゲートの開口部は小さいが、中はかなり広い。このあたりの割り切りも潔い。フロントウインドウは世界初採用の曇りにくいガラス(eXeview)だが、これは実際に走行し、雨の日や湿気の多い日を体験してみなければわからない。
エンジンを掛ける。まだナンバーは付いていないので、場内を少しだけ移動させるだけだ。ディーラーオプションとして、COPEN Coupe発売を機に、HKS社とコラボしたスポーツマフラーとサスペンションキットが販売されることになった。さらにフロントデフにはフロントスーパーLSDが標準装備(MT車)されている。車重はルーフだけで20㎏の軽量化なので、走りはかなり楽しめそうだ。これらを装備したCOPEN Coupeが公道を疾走するところを想像するだけでワクワクしてきた。
コンセプトカーを生産化するむずかしさとは

コンセプトカーとして出展されていたクルマが「COPEN Coupe」として生産化されることになった。
文章で書くとたったこれだけだが、実際にコンセプトカーを生産車にまで仕上げるのはとても大変な作業だ。ショーなどで観客の注目を集めるために製作されるクルマは、目立つことが大切。そのために外観には、特別な素材を使ったり、手づくりでなければできないような車体の面や線の構成を行う。そこにはコストや作業時間などの要素はほとんど入ってこない。
そのような環境の中で完成したモデルを、来場者からの評判がよかったからといって、生産化させるのは、無謀に近いものがある。生産化するクルマは販売台数や当然のことだが会社としての利益も大切。そこには、開発チームの熱意だけでなく、経営陣の理解もなければ実現しないという現実があるのだ。
しかし、「COPEN Coupe」は、求めるお客様の声に応えるという形で誕生した。ここにダイハツのものづくりの姿勢がある。
ダイハツのクルマづくりの歴史は挑戦の歴史

ダイハツの100年以上のクルマづくりの歴史を調べてみると、おもしろいクルマ、こだわりの強いクルマ、マニアックなクルマが多いことに気付く。おそらく、国産自動車メーカーのなかで、もっともチャレンジャブルなメーカーではないか、と思ったりするのだ。
例えば1960年代、ダイハツが初めて軽自動車よりも大きい小型車をつくろうとしたとき、デザインをイタリアのカロッツェリアの大御所であるヴィニャーレというデザイナーに依頼。しかもそのクルマはいまでいうステーションワゴンだった。これはおしゃれ度ナンバー1。そのモデルはワゴンから4ドアセダンにも展開、さらにルーフを切り取り4人乗りのオープンスポーツカー、スパイダーまでつくったのだ。日本で初めて公道を走行できるバギィカー「フェローバギィ」は70年代に入ってから。80年代にはイタリアのスーパーカーメーカー デ・トマソと組んで、シャレード・デ・トマソというチューンドモデルをつくっている。軽自動車「リーザ」をベースにオープンカー 「リーザ・スパイダー」は90年代だった。
ここに挙げたクルマは、当然だが台数を稼げるクルマではないが、実は、こうしたクルマづくりがダイハツのものづくりの姿勢を表わしているといえるのだ。
クルマづくりを「文化」としてとらえるダイハツ

海外、とくに欧州の自動車メーカーは、どう考えても販売台数を期待できそうもないモデルも生産している。オープンカーや2ドアクーペのようなクルマだ。なぜこのようなハッキリ言って売れないクルマもつくるのか。日本の自動車メーカーにはない考え方だ。
その理由は、クルマは文化だから。単なるA地点からB地点への移動手段ではない、ととらえているからだ。そのクルマが必要だという人が1人でもいるならつくり続ける。この姿勢を守り続けている。こだわりのクルマづくりといえる。

日本のメーカーに目を向けてみる。ダイハツが初代COPENを発売したのが02年。既存のシャーシを用い、独自のリトラクタブルルーフを開発している。さらに節目ごとにスペシャルバージョンを発表するなど、積極的にクルマを開発してきた。販売台数の見込めそうもないスポーツカーにここまでお金をかけるというのは、日本の自動車メーカーとしてはかなり異例のことだ。
社内にクルマ好きはいるが、全社的に、とくに経営陣がOKしなければ、こうしたクルマづくりはできない。しかも、COPENは1代限りではなかった。14年にフルモデルチェンジして、登場した。現行型はなんとシャーシまで新しく開発し、軽量でボディ剛性も高く、本格スポーツカーの方向でつくられていた。ボディも3タイプ用意した。これって、世界中の自動車メーカーを見渡しても、実施しているメーカーは、ダイハツだけ。そこまでしても、販売台数は限られているはず。それでもCOPENというクルマを必要だと言ってくれるユーザーが少なからず存在している。これはもう「お客様の声に形で応える」という範囲を超えたクルマづくりだ。
ショー用のコンセプトカー完成から2年もかけて生産化した「COPEN Coupe」は、ダイハツのお客様に寄り添うこだわりのクルマづくりの思想から生まれたスーパースポーツカーなのだ。